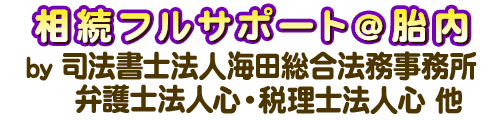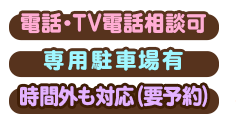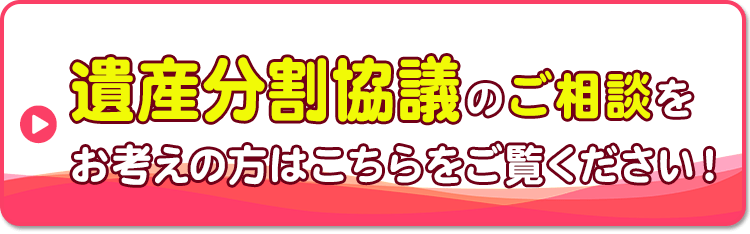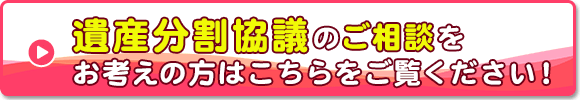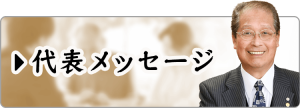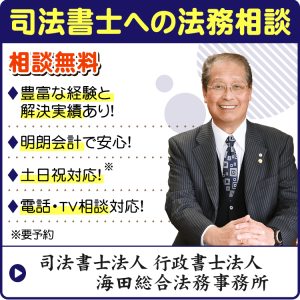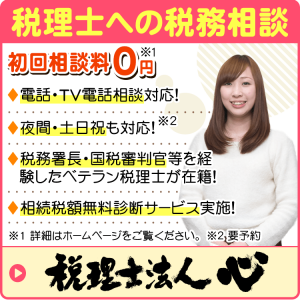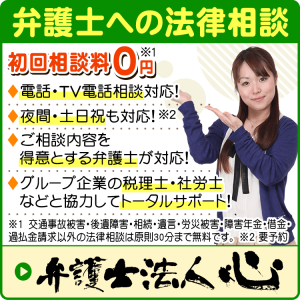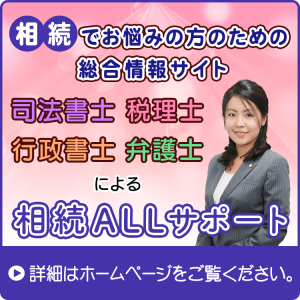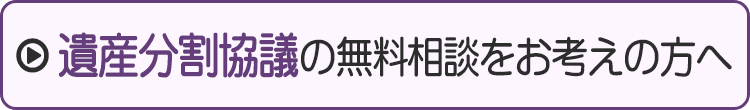一方的な遺産分割協議書が送られてきた場合の対応
1 一方的な内容の遺産分割協議書が送られてきた場合の対処法
本来、遺産分割は相続人同士で話し合って内容を決めるものですが、現実には、被相続人がお亡くなりになった際に、何の相談もなく、他の相続人が決めた遺産分割の内容が書かれた遺産分割協議書が送られてくるということがあります。
このような場合、往々にして他の相続人に有利な内容が書かれており、かつその相続人には円満に遺産分割をする気がない可能性があるため、その遺産分割協議書に署名押印はせず、まず弁護士にご相談ください。
もし署名や押印をしてしまうと、一方的な内容の遺産分割協議が確定してしまい、基本的には取り消すことができなくなるためです。
その後、弁護士を代理人として遺産分割の話し合いを試み、それでも遺産分割協議が成立しない場合には、家庭裁判所での調停や審判を行います。
2 弁護士を代理人とした遺産分割の話し合い
遺産分割協議を弁護士に依頼すると、一般的には、まず弁護士から他の相続人に対して受任通知という書面を送付し、遺産分割協議の話し合いを行いたい旨や、以降の連絡窓口は代理人弁護士となる旨を伝えます。
その後、基本的には民法で定められているルールに基づいた遺産分割をするべく、弁護士が他の相続人と具体的な交渉を進めていきます。
他の相続人の態度が変わり、遺産分割協議に応じるようでしたら、合意形成をして遺産分割協議書を作成します。
もっとも、実務においては、連絡を取ることを拒絶したり、一切主張を変えない相続人も存在します。
話をまったく進められない場合には、家庭裁判所で調停および審判を行います。
3 家庭裁判所での調停や審判
家庭裁判所に遺産分割調停を提起すると、調停委員を介した話し合いの期日が設けられます。
遺産分割調停は、あくまでも相続人同士の話し合いではありますが、個別の交渉では話し合いに応じなかった相続人も、調停になると話をするようになることがあります。
話し合いは、一般的には、相続人が交互に調停委員がいる部屋に入り、言い分等を伝えるという形式になりますので、相続人同士が顔を合わせることはあまりありません。
遺産分割の内容について合意に達することができた場合には、その内容を記した調停調書を作成し、遺産分割調停は終了となります。
一方、他の相続人が調停を完全に無視するケースや、強硬な主張を一切崩さずに話が平行線になり続けるケースというのも、実際にはあります。
このような場合には、審判に移行し、家庭裁判所が各相続人の言い分や提出された資料等をもとに、法律に従って遺産分割の内容を決めます。